建築職公務員を目指している方の中には「市役所の仕事ってどんな内容だろう?」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
建築職員が配属される部署は「建築審査部門」「まちづくり部門」「営繕部門」の3つに分類されます。この記事では、その内「営繕部門」の仕事内容について解説します。
この記事を読めば、「営繕部門」の仕事内容や、残業は多いのか?などについて分かります。建築職公務員を目指している方は最後までお読みください。
営繕部門とは
営繕部門とは公共施設の設計や工事を担当する部署を指します。
主な公共施設には、「市役所や公民館、消防署、コミュニティーセンターや学校」などがあります。
営繕部門の主な仕事内容は次の3つです。
①工事が設計書のとおり行われているか進行管理する仕事。
②設計書が市の基準に沿って設計されているか確認する仕事。
③経年劣化などによる公共施設の損傷部分を補修する仕事。
それでは、仕事内容について見ていきましょう。
【仕事内容】
①工事が設計書のとおり行われているか進行管理する仕事

一つ目は、公共施設の建物を工事する際に、工事が設計書のとおりに行われているか進行管理する仕事です。ここでいう工事とは、新築、増築、改修など、完了まで数ヶ月かかるものを指します。
工事は市の職員が自ら行うことはできませんので、工事業者と契約を行い工事を依頼します。市の職員は、契約した工事業者が、設計書や契約書のとおりに工事しているかを確認します。
契約から工事完了までの流れ
工事業者と契約してから工事完了までの流れは次のとおりです。
- 契約
- 打ち合わせ(顔合わせ、工事スケジュールについて)
- 工事対象の施設の職員に工事スケジュールなどを説明
- 近隣に住んでいる方へ工事のお知らせ
- 工事開始
- 中間検査(配筋、コンクリート打設)
- 工事完了
- 担当職員検査
- 工事書類の確認
- 完了検査
工事が始まると、市の職員は工事業者の現場代理人と協力しながら工事完了に向け、進めていきます。
市の職員の仕事
実際に工事を行うのは業者です。では、市の職員は何をするのでしょうか。
契約〜工事開始
契約後、市の職員は工事に向けて、関係者と事前調整を行います。工事業者とは、工事スケジュールや、搬入経路などについて、打ち合わせを行います。
近隣住民に対して工事のお知らせを行うのも市の職員の仕事です。工事期間中は周辺道路に大型の資材搬入車が走行が増えるので、注意喚起も兼ねて行います。(工事規模が大きい場合は説明会を開催することもある。)
工事開始〜工事完了
工事開始後、市の職員は工事が適切に行われているか進行管理を行います。
市の職員の仕事の一つは書類の確認です。工事の各工程を行う前に、工事の施工手順などについて記載された施工計画書が工事業者から提出されます。市の職員は、施工計画書の内容が求めている仕様(グレード)になっているか、安全対策はしっかり行われているかなどを確認します。市の職員の仕事は7割程度が書類の確認です。
工事業者に指示することも市の職員の仕事です。工事では、設計書と現場が異なっていることがあります。(壁を解体したら、想定していた構造と違った)内容によっては、工事が中断する場合もあるので、素早く工事業者に指示することが重要です。

近隣住民から工事に対するクレームが来ることもあります。その対応も市の職員の仕事です。
検査
工事の検査をするのも市の職員の仕事です。例えば配筋検査です。コンクリート打設後、配筋は目視できなくなるので、必要なピッチで鉄筋が配置されているかなどを工事の途中で検査します。工事完了後は、市の職員が設計書のとおり工事が行われているか確認します。塗装が剥げているなどの不備がある場合には、工事業者に修正を指示します。

完了検査は、工事検査部門に依頼します。
②設計書が市の基準に沿って設計されているか確認する仕事

設計事務所に委託した設計が、要求どおりに行われているか確認するのも営繕部門の業務です。設計業務についても、設計事務所に委託することが多いです。
契約から設計完了までの流れ
契約から設計完了までの流れは次のとおりです。
- 契約
- 打ち合わせ(契約内容、設計内容の確認)
- 現地調査(設計事務所、市)
- 図面の作成(設計事務所)
- 図面の確認、修正指示(市)
- 修正図面の提出(設計事務所)
- 検査
市の職員の仕事
市の職員は、設計事務所に委託した設計が、市の要求のとおりに行われているか確認します。市の仕様に則った設計となっているか、図面に不足している情報はないか、もっと良いレイアウトはないかなど、予算を気にしつつ、設計事務所に指示をします。

図面枚数は大きな工事の場合、100枚を超えます。全ての図面を確認するのは根気のいる仕事と言えます。
③経年劣化などによる公共施設の損傷部分を補修する仕事

公共施設の補修を行うのも営繕部門の仕事です。公共施設は建築から年数を経過しているものも多く、あちこちがボロボロです。建物の補修が必要な場合は、市の職員が工事業者の手配をします。
経年劣化により起きる破損
経年劣化により起こることとしては、主に次のものが考えられます。
- 外壁(塗膜、モルタル)の落下
- 雨漏り
- 建具の破損
このような事態が起きた場合には、速やかに現地確認した上で、業者に修繕の依頼を行います。
修繕する場合の流れ
修繕する流れは次のとおりです。
- 業者連絡
- 現地確認
- 見積もり取得
- 事務手続き
- 修繕
担当職員は、修繕内容に対応できる業者に連絡を行い、日程調整を経て、現地確認を行います。見積もりを取得し、市役所内の事務手続きを経て、業者に修繕を依頼します。金額によっては、複数社から見積もりを依頼する必要もあります。
修繕業務は緊急対応が必要な場合があります。日頃からどの業者がどんな修繕に強いのかを知っておくことが大事です。また、沢山の業者と連絡しやすい関係性を日頃から築いておくと、業務が円滑に進みます。
【残業時間】
私が、営繕業務を行っていた時の平均残業時間は月30時間程度でした。営繕業務は時期によって、業務量が変動します。忙しい時期には月50時間程度、忙しくない時期は、月10時間程度でした。
忙しい時期は10月.11月.1月.2月
私が営繕業務を行っていた時の忙しい時期は10月.11月と1月.2月でした。
10月.11月
10月.11月は工事の完了検査に向けた準備のため、忙しくなる傾向があります。工事の契約は6か月又は1年の期間であることが多く、上半期の工事完了時期は10月.11月です。完了検査に向けて、工事書類の確認を行うのですが、本当に膨大な量です。
1月.2月
1月.2月については、工事の完了検査に向けた準備に加えて、次年度の契約準備のため特に忙しくなる傾向があります。
【営繕業務の良い点】
私が営繕業務を経験して良かった点は主に次の3つです。
建築の構造や材料の知識が身につく
営繕業務を経験すると、建築物の構造や材料の知識が身に付きます。営繕業務では、実際に工事現場に足を運び工事の様子を見学することができます。解体中には壁の内側や天井の裏などの普段見れない部分を見ることができます。
また設計業務を経験すると図面表現を学ぶことができます。設計業務では、設計事務所から提出された図面を確認します。設計業務を通じて、例えば「建具は図面上どのように表現するのか」などを学ぶことができます。
CADの操作能力が上達する
営繕業務を通じてCADの操作が上達します。設計業務の中で、設計事務所から提出された図面を市の職員が修正をかけることがあります。少量の図面であれば市の職員が自ら図面を作成することもあります。図面の作成・修正を重ねることで、CADの操作が上達します。
市民からの問い合わせが少ない
営繕業務は市民と連絡を取り合うことは基本的にありません。調整相手が公共施設の管理者と設計や工事などの契約先になるからです。市民からの連絡が無いため、電話対応に苦慮することは比較的少ないと言えます。
【営繕業務のつらい点】
営繕業務のつらい点は次のとおりです。
休日にも工事業者から連絡が来る
工事期間中には、休日にも工事業者から連絡が来ることがあります。工事は休日にも行われているため、事故が起きた場合や、図面と現場の相違があった場合には、業者から連絡が来ます。休日でも仕事が気になってしまう所が営繕業務のつらい所です。
突発的な対応が求められる
工事中の事故や、外壁が落下した場合などには状況確認などの早急な対応が求めらます。その際には、事務所内での作業を中断して現場に向かうことになるので、他の業務が滞ることがあります。
まとめ
営繕部門は建築職公務員の配属先の中でも、特に建築らしい仕事と言えます。大変なことも沢山ありますが、建築について学ぶことも多い仕事です。この記事が参考になれば幸いです。
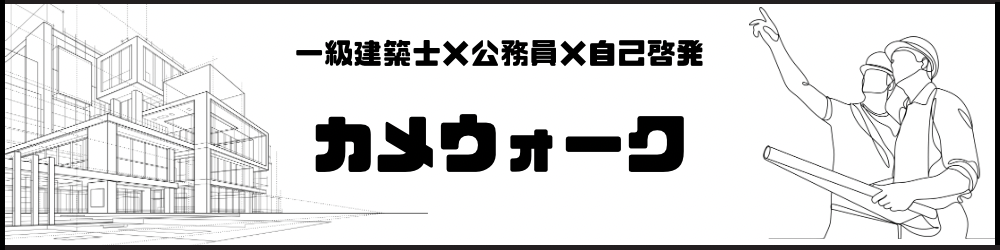
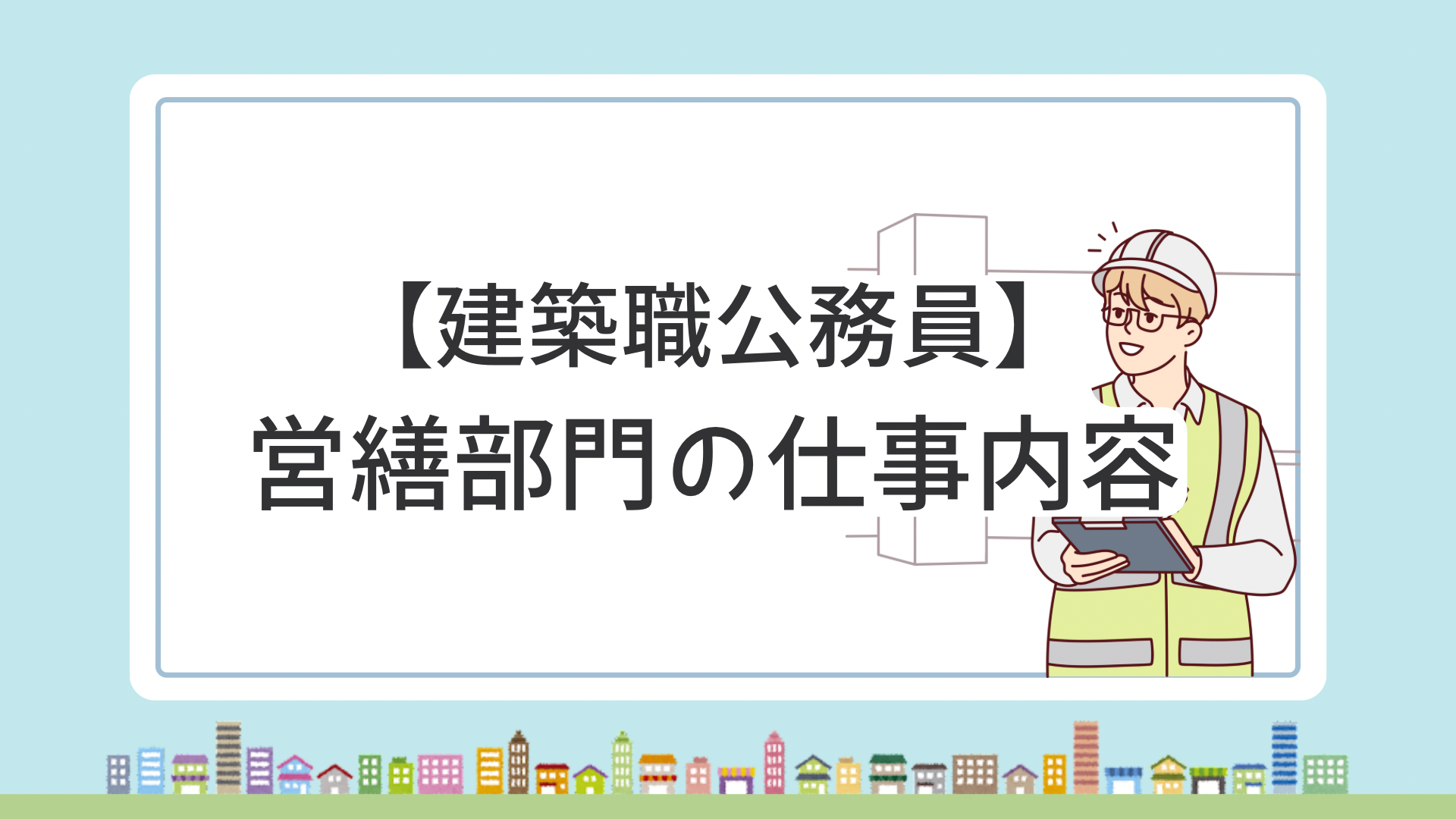


コメント