今回は、建築職公務員として働こうと考えている方に、「建築職公務員のつらいこと3選」をお伝えします。
建築のことなら何でも知っていると思われている
建築職は全体の職員数に比べて少数であるため、必然的に事務職員に囲まれて仕事をします。
そのような環境で感じることとしては、「建築職は建築の大学を卒業しているため、当然、建築基準法に詳しい。と思われている。」です。
もちろん、建築職であるからには、建築基準法に詳しくあるべきと思います。
しかし、実際のところ、大学では、デザインの授業が中心で、建築基準法を深く理解する機会はありません。

建築審査業務を経験しないと、建築基準法の理解はなかなか深まらない印象です。
特に建築職が少ない職場、まちづくり系の部署に配属されるとさらに大変。
班に建築職一人だけということもあります。同じ部署の中で、建築について疑問点が生じれば、すぐに話が回ってきます。
聞かれた時に「分かりません。」では、職場内の立場も危なくなってしまうので、日頃から勉強を怠らないことが大切ですね。
どんな職場に異動するか分からない
公務員の宿命ともいえる異動。建築職も例外ではありません。
建築職であれば、建築に関する部署への配属となるので、行政職と比べたら異動先は限られています。
それでも、異動は転職のようなもの。部署が変われば仕事内容も周りの人間も一新されます。
建築職が配属となる部署は主に、「建築審査部門」、「営繕部門」、「まちづくり部門」の3つに分類されます。
その中でも、まちづくり部門については、建築基準法よりも都市計画法を主に扱う印象です。
建築職なのに、建築にしばらく触れなくなることもあります。
建築職として採用されたからには、建築の知識を伸ばしたいと思っている方には、まちづくり部門への配属は合わないかもしれないですね。

常に建築に触れて仕事したいと思っていたので、私はまちづくり部門と合いませんでした。
建築のエキスパートにはなれない
建築のエキスパートにはなれないことも建築職公務員のつらいところです。「この分野なら誰にも負けない。」と言えるほど、知識や経験を積むことは難しいと感じます。
例えば、営繕部署に配属となり公共施設の工事を担当する部署に配属されたとしても、実際に工事するのは建設業者。設計についても、設計事務所に委託して、市の職員はというと、計画どおり工事が進んでいるかの確認。上がってきた設計書が標準的な仕様にあっているかのチェック。
このような受け身の仕事内容だと、どうしても民間の方たちに知識や経験で勝てるものはありません。
唯一、公務員が民間に勝てるものは建築基準法への理解かと思いますが、これも、異動により、突き詰める前に業務を離れることになります。

業務に慣れてきたと思ったら、異動というのは、公務員あるあるですよね。
まとめ
ここまで、建築職公務員のつらいところを紹介してきました。建築職公務員となった後に、ギャップを感じることがないよう、この記事が参考になれば嬉しいです。
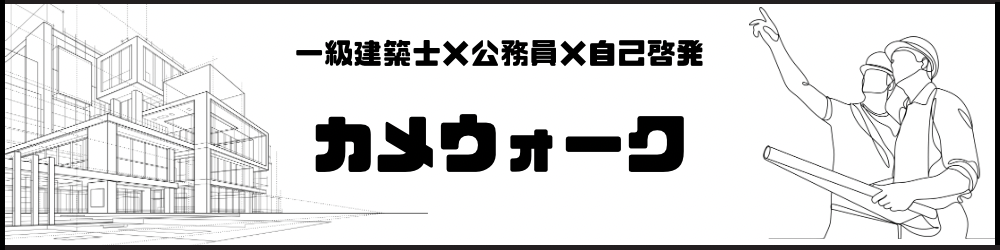
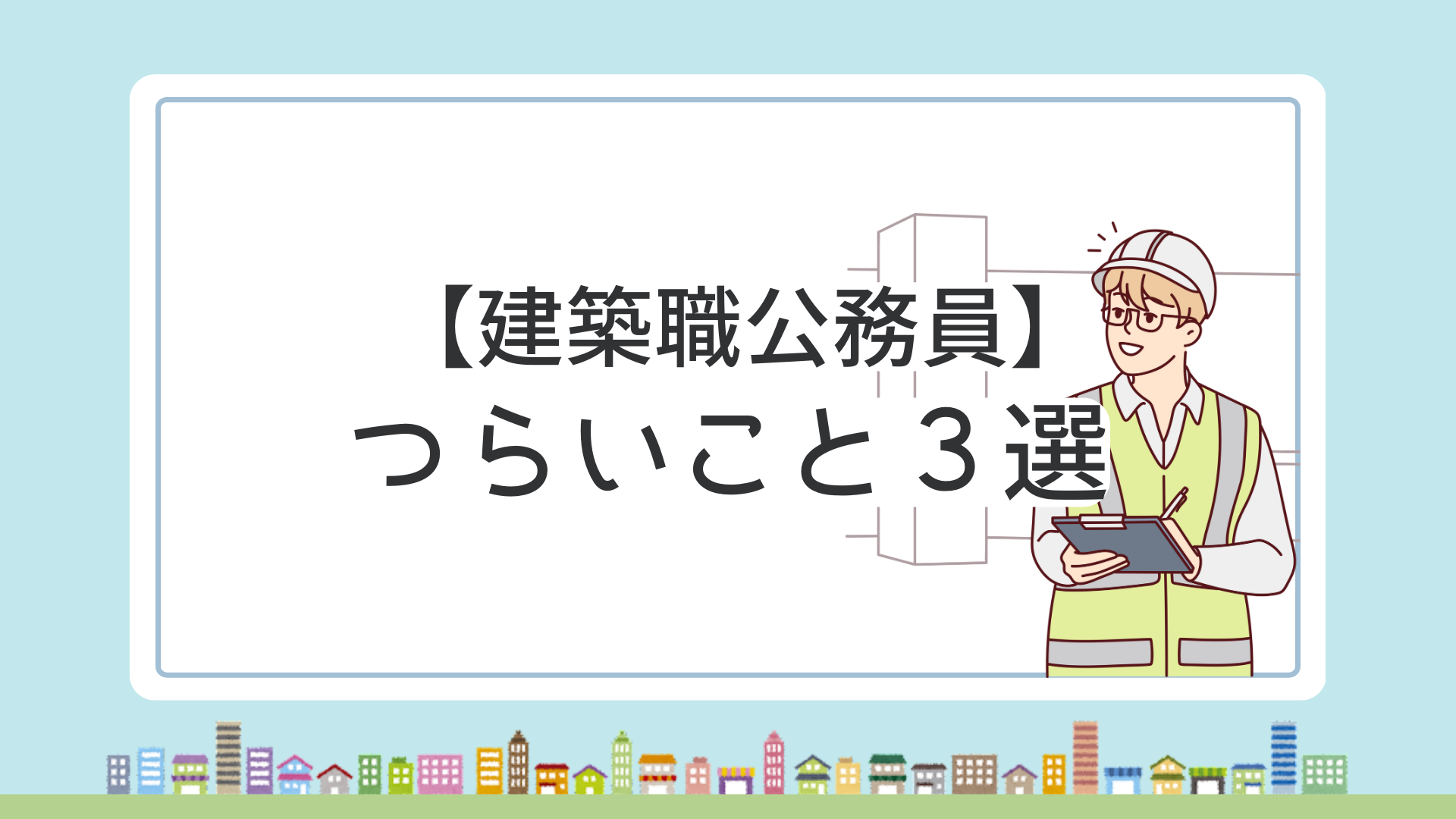
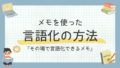

コメント